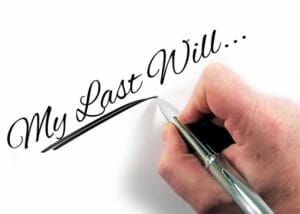推定相続人の廃除と留意点

今回は「推定相続人の廃除」について確認していきます。
廃除には慎重な判断が求められますが、まずはその制度の概要をつかんでおきましょう。
コンテンツ
推定相続人の廃除
被相続人は、推定相続人に一定の事由(廃除事由といいます)があるときにその者を「廃除」することができます。
相続人から権利を奪う制度
正確には家庭裁判所に廃除の請求をすることになりますが、廃除は単に感情的に相続させたくない人物がいるといった程度では認められません。
なぜなら、廃除には相続人から当然に与えられるべき「相続」という権利を奪うという意味合いがあるからです。
そのため被相続人に対する虐待や重大な侮辱といった著しい非行が認められる場合に限り、廃除をすることができるとされています。
遺言による廃除
遺言によっても推定相続人の廃除を行うことができますが、この場合には遺言執行の段階で既に死亡している遺言者(被相続人)、つまり虐待や重大な侮辱を受けていた者から直接その内容を家庭裁判所に伝えることができません。
そのため廃除事由の立証という観点をもって遺言書を作成する必要があります。
一つの方法として、公正証書遺言で廃除事由となる事実を記しておくことも有用でしょう。
公正証書という書類の性質上、自筆証書遺言よりも証拠資料としての価値が高く、また作成時においても公証人と文案を擦り合わせることでしっかり廃除事由を記載することもできるためです。

推定相続人の廃除は遺言ですることもできるが、具体的な廃除事由が必要
遺言による廃除に関する留意点
遺言によって推定相続人の廃除をする際の留意点をいくつか挙げておきます。
遺言執行者の指定を忘れずに
上記した遺言による廃除ですが、これには遺言執行者の選任が必要になります。
遺言の効力が生じた後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をするという手順になりますが、万が一遺言執行者が指定されていないような場合はまず遺言執行者の選任から始めなければならず、遺された者の負担が大きくなります。
遺言による推定相続人の廃除をする際は遺言執行者の指定も同時にしておくことが大切です。
【遺言執行者についての記事はこちら】
プライバシー侵害の恐れもある
遺言にどこまで具体的に廃除事由の事実を記載するかという点にも注意が必要です。
遺言書はその内容を相続人だけでなくその関係者を含め多くの人が目にする可能性が高い文書といえます。
ここに被相続人への虐待や重大な侮辱の事実を事細かに記載してしまうと、名誉やプライバシーの侵害にかかる諸問題が発生する可能性があるのです。
公正証書遺言には抽象的に廃除事由に該当する事実があったことのみを記載し、宣誓認証など別の方法も併用して具体的な立証を試みるケースもあるようです。

遺言による廃除の際は、遺言執行者の選任、プライバシー侵害への配慮といった点に留意する
廃除の取消し
最後に、推定相続人の廃除は取り消すことができることも付け加えておきます。
廃除を取り消す場合は、特にその理由等の記載を求められることはなく単に被相続人の意思が認められればよいので、廃除するときに比べてそのハードルは低いです。
家庭裁判所に請求すること、遺言によることができること、またその際には遺言執行者の選任が必要であることは廃除する場合と同様です。

被相続人はいつでも推定相続人の廃除の取消しを行うことができる
まとめ
今回は「推定相続人の廃除」についてその概要を確認しました。
- 廃除には具体的な廃除事由が必要
- 遺言による廃除には遺言執行者の選任やプライバシーへの配慮等が必要
- 被相続人はいつでも廃除の取消しができる
推定相続人を廃除するということはその者から権利を奪うことに他なりません。
後に取り消すことができるといってもそこに負担が発生することは避けられませんから、推定相続人の廃除はいっときの感情ではなく冷静な判断をもとに行うことが求められます。