民法と遺言①:遺留分
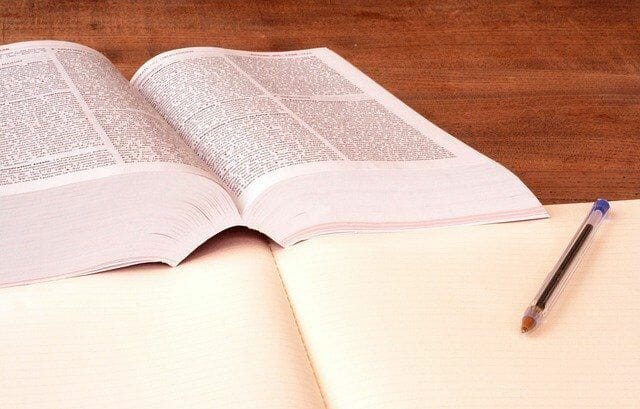
今回は遺言を残す場合に注意を要する「遺留分」に焦点を当てます。
民法の規定を参考にその概要を確認していきましょう。
コンテンツ
遺留分の帰属およびその割合
「遺留分」は兄弟姉妹以外の相続人、つまり被相続人の配偶者、子および直系尊属(父母や祖父母)に対して認められます。
簡単にいえば、これらの者に対して最低限の相続分を保障したものが遺留分であるといえます。
民法第1042条では遺留分の算定の仕方を規定しています。
総体的遺留分:遺留分権利者全体としての割合
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、(中略)遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
民法第1042条第1項柱書(一部省略)
第1042条第1項では総体的遺留分つまり遺留分権利者全体としての遺留分割合を規定しています。
これに対して、相続人各自が請求できる具体的な割合を個別的遺留分といい、第1042条第2項に定めがあります。
まずは総体的遺留分から確認していきましょう。
直系尊属のみが相続人:総体的遺留分は3分の1
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
民法第1042条第1項第1号
被相続人の父母や祖父母のみが相続人である場合、遺留分は3分の1になります。
例えば、遺言者の相続人が父母のみのケースで遺言者が遺言により相続人以外の者にその全財産を遺贈するとした場合、遺言者の父母は遺留分侵害額請求を行うことで3分の1の財産を相続することができます。
上記以外:総体的遺留分は2分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
民法第1024条第1項第2号
配偶者や子が相続人となる場合の遺留分は2分の1です。
相続人が配偶者のみの場合、配偶者と第1順位相続人(子など)の場合、そして配偶者と第2順位相続人(父母や祖父母)の場合が該当します。
個別的遺留分:総体的遺留分×法定相続割合
相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
民法第1042条第2項
第1042条第2項は個別的遺留分つまり相続人各自の具体的な遺留分割合を規定しています。
その算定は、まず総体的遺留分(2分の1か3分の1のいずれか)を把握し、それを各相続人の法定相続割合で乗じる方法によります。
例えば、父母のみが相続人となる場合は、総体的遺留分3分の1に2分の1を乗じた6分の1が父、母それぞれの遺留分となります。
少々ややこしいですが、他のケースも総体的遺留分×法定相続割合で算定できます。
ポイント①(遺留分の帰属およびその割合)
<遺留分権利者>
配偶者、第1順位相続人(子など)、第2順位相続人(父母や祖父母)
- 第3順位相続人(兄弟姉妹など)は遺留分を請求できない
<総体的遺留分>
直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1
- (例)父母のみが存命の場合、全体で3分の1
- (例)配偶者と父母のみが存命の場合、全体で2分の1
<個別的遺留分>
総体的遺留分×法定相続割合
- (例)父母のみが存命の場合
- 父・母各6分の1(総体的遺留分3分の1×2分の1)
- (例)配偶者と父母のみが存命の場合
- 配偶者6分の2(2分の1×3分の2)、父・母各12分の1(2分の1×3分の1×2分の1)
遺留分を算定するための財産の価額
遺留分の算定対象となるのは全ての財産ではありません。
算定する財産については民法に以下の規定があります。
相続財産+贈与財産-債務
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
民法第1043条第1項
第1043条第1項から、相続財産+贈与財産-債務=遺留分の対象財産という式が導き出せます。
次に贈与財産についてもう少し詳しく見てみましょう。
贈与財産①:相続開始前の1年間にしたもの
贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。(後略)
民法第1044条第1項(前半部分)
遺留分に含まれる贈与財産は遺言者の死亡前1年間にしたものに限られます。
つまり、上記の式は相続財産+(相続開始前1年間の贈与財産)-債務=遺留分対象財産となります。
さらに第1044条第1項には続きがあります。
贈与財産②:当事者双方が悪意で行った贈与
(前略)当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
民法第1044条第1項(後半部分)
当事者双方、つまり遺言者と受贈者が遺留分を減らす目的(悪意)で行った贈与については、相続開始前1年間という限定がつかず全て遺留分の対象となります。
他にも詳細を規定する条文がありますが、ここまでをまとめた最も基本的な式は以下のようになります。
ポイント②(遺留分を算定するための財産の価額)
<基本式>
遺留分対象財産=相続財産+贈与財産-債務
⇒上記の式に含まれる贈与財産は以下のいずれかに該当するものを指す
- 相続開始前1年間の贈与
- 当事者双方が悪意で行った贈与
受遺者または受贈者の負担額
では、遺留分侵害額請求を受けた者の負担については民法はどのように規定しているのでしょうか。
受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(略)又は贈与(略)の目的の価額(略)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
民法第1047条第1項柱書(一部省略)
ここでは簡明な解説のために条文内のかっこ書きは省略していますが、以下に示すように第1047条第1項の各号において具体的な負担方法が列挙されています。
相続開始時点に近い者から負担する
一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 (略)
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
民法第1047条第1項第1号・第3号
「受遺者」とは遺贈を受けた者、「受贈者」は贈与を受けた者をいい、「遺贈」は遺言による贈与を指します。
第1号が示していることは、遺留分の請求を負担する順番は、①遺贈を受けた者→②贈与を受けた者であるということです。
そして第3号は受贈者が複数のときは、後に贈与を受けた者から負担するとしています。
ということは、財産を受け取ったタイミングが遺言者の死亡時に最も近い者から順に遺留分侵害額を負担していくことになります。
「複数」の受遺者または「同時」の受贈者のケース
第3号のかっこ書き「前号に規定する場合を除く」の「前号」は以下の規定です。
目的の価額の割合に応じた負担
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。(後略)
民法第1047条第1項第2号(本文)
受遺者は遺言により贈与を受ける者なので複数ある場合には「同時」に遺贈を受けたことになります。
また贈与についても「同時」に複数の者を受贈者として行うことも考えられます。
第2号の規定はこのような場合、それぞれが受け取った財産の価額を基準にその割合で遺留分侵害額を負担するという原則を示しています。
遺言による意思表示の尊重
例外として遺言者が遺言において別段の意思を表示したときにはそれに従うとしています。
二 (前略)ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法第1047条第1項第2号(ただし書)
別段の意思とは例えば、
「遺留分侵害額請求があったときは、まず現預金、次に株式から負担するものとする。」
というもので、このケースでは現預金を受け取った者がまず遺留分侵害額を負担し、それでも足りない場合に株式を受け取った者が負担することになります。
ポイント③(受遺者または受贈者の負担額)
<遺留分侵害額負担の基本パターン>
財産を受け取ったタイミングが相続開始時点に近い者から負担する
(例)受遺者A(令和2年4月1日遺言者死亡)、受贈者B(令和2年3月1日受贈)、受贈者C(令和2年1月1日受贈)の3人がいる場合
- 遺留分侵害額の負担はA→B→Cの順に行う
<受遺者が複数いる場合、同時に贈与を受けた者が複数いる場合>
・原則:受け取った財産の額に応じた割合で負担する
(例)受遺者A(遺贈価額1,000万円)、受遺者B(遺贈価額500万円)の2人がいる場合
- A2:B1の割合で負担する
・例外:遺言者が遺言に別段の意思を表示したとき
(例)受贈者A(令和2年1月1日現預金1,000万円受贈)、受贈者B(令和2年1月1日株式1,000株受贈)の2人がいる場合
⇒遺言「遺留分侵害額請求があったときは、まず現預金、次に株式から負担するものとする。」
- まずAが負担し、それでも足りないときはBが負担する
遺留分侵害額請求権の期間の制限、遺留分の放棄
最後に、期間の制限や遺留分の放棄についても確認しておきましょう。
時効による1年または10年経過での消滅
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
民法第1048条
遺留分を侵害された者は、いつまでもその請求をすることができるわけではありません。
相続が開始したことや遺贈があったことなどを知った時(主観的起算点)から1年間、もしくは相続が開始した時(客観的起算点)から10年間行使しなければ、時効によって消滅します。
相続開始前の遺留分放棄
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
民法第1049条第1項
遺留分は法定相続人の生活保障や相続への期待の保護といった目的のもとに規定されているため、相続が開始する前にその権利を放棄するには一定の制限がかかります。
すなわち家庭裁判所の許可がある場合に限って、相続開始前の遺留分放棄が認められるのです。
ポイント④(遺留分侵害額請求権の期間の制限、遺留分の放棄)
<期間の制限>
・主観的起算点から1年経過で請求権は時効消滅
- 主観的起算点:相続の開始や遺贈があったことなどを遺留分権利者が知った時点
・客観的起算点から10年経過でも請求権は時効消滅
- 客観的起算点:相続が開始した時点
- 遺留分権利者が知っているか否かは問題にならない
<遺留分の放棄>
相続開始前の放棄には家庭裁判所の許可が必要
- 遺留分制度には相続人の生活保障、相続への期待の保護といった目的がある
まとめ
今回は遺留分に関しての民法の規定を確認しました。
- (個別的)遺留分=総体的遺留分×法定相続割合
- 遺留分対象財産=相続財産+贈与財産-債務
- 財産を受け取ったタイミングが相続開始時点に近い者から負担
- 1年(主観的起算点)または10年(客観的起算点)で時効消滅
- 相続開始前の放棄には家庭裁判所の許可が必要
まだまだ論点はたくさんある分野ですが、上記5つは最低限押さえておきたいポイントといえます。
遺言を残す場合には、
- 遺留分を侵害しない遺言を作成する
- 遺留分を侵害する場合、その理由等を付言事項に記しておく
といった対策をとることで円満な相続の実現を目指しましょう。
